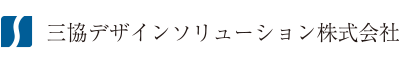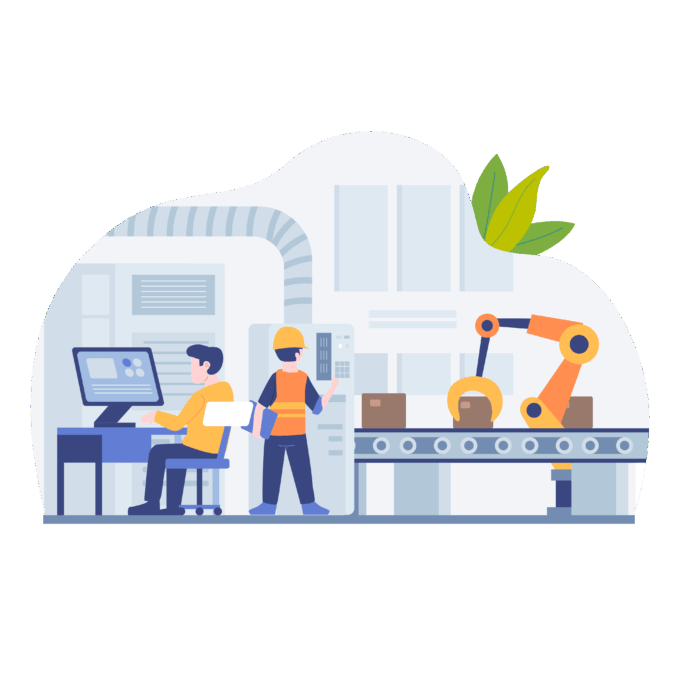受付時間 月曜~金曜 8:45~17:45
ピックアンドプレースとは?自動化の基本動作をご紹介
製造現場でよく耳にする「ピックアンドプレース」という言葉。
これは 部品をつかんで(Pick)、別の場所に置く(Place)というシンプルな動作を指します。
一見すると単純ですが、実は自動化設備やロボットに欠かせない重要な技術です。
ピックアンドプレースが活躍する場面
電子部品実装
基板にチップ部品を高速で配置するマウンターは、まさにピックアンドプレースの代表例です。
部品搬送・組付け
協働ロボットや直交ロボットが部品をつかみ、治具に落とし込むといった作業で活用されます。
検査工程
ワークをカメラの前に正確に持っていくための動作としても使われます。
梱包・仕分け
完成品をトレイや箱に整列させる工程にも、ピックアンドプレースは欠かせません。
ピックアンドプレースの構成要素
- エンドエフェクタ(ハンド/グリッパー)
- 吸着パッド(真空で部品を吸い上げる)
- メカチャック(指でつかむように保持)
- 専用治具(特殊形状に合わせた把持具)
- ロボット/アクチュエータ
- 直交ロボット、スカラロボット、協働ロボットなど
- 高速・高精度な動作が可能
- 位置決め・ガイド
- V溝やテーパーを利用して自然に位置が決まる仕組み
- 斜めアプローチやチルト挿入によるガイド動作
- ビジョンシステム
- カメラで部品の位置を補正
- OK/NG判定や種類判別にも利用
- 制御システム(PLC・コントローラ)
- ロボットやセンサーの信号を管理
- タクトタイムに合わせて最適な動作を実現
なぜピックアンドプレースが重要なのか?
ロボットは繰り返し精度が高く、同じ位置に安定して配置できます。
人の手よりも速く、効率的に部品を扱うことが可能です。
繰り返し作業を自動化することで、人はより付加価値の高い業務に集中できます。
導入事例:自動車部品組立工程における労働生産性向上
ある自動車用ヒューズ組立工程では、オペレーターが 薄銅板ワークを1枚ずつ治具に位置決め投入し、
さらに設備に供給する 作業を終日実施していました。
この単純反復作業に対し、UR協働ロボットを活用したピックアンドプレースシステムが導入されました。
導入ポイント
- インデックス装置によるワークの一枚取り出し
- 真空吸着式ロボットハンドによるワークの把持
- 受け治具への位置決め投入
- 治具ごとの設備投入
導入効果
| 項目 | 導入前 | 導入後 | 改善効果 |
|---|---|---|---|
| 作業方法 | 作業員が薄銅板ワークを1枚ずつ手作業で治具に投入、その治具を設備にセット | インデックス装置でワークを切り出し → ロボット(UR3)が真空吸着でピック → 受け治具に投入 → 治具ごと設備投入 | 単純反復作業をロボットに置き換え |
| 担当人員 | 1名(終日付き切り) | 1名(2時間ごとのワーク供給のみ) | 作業負荷を大幅軽減 |
| 作業時間 | 8時間 | 0.3時間 | 約1/27に短縮 |
| 品質 | 手作業によるばらつきあり | ロボットによる安定した位置決め | 均一化・品質向上 |
| 安全性・稼働率 | 安全柵必須、設備稼働効率に制約 | 安全柵レス、着脱式コントローラーで稼働率向上 | 作業環境改善 |
ピックアンドプレースは“ロボット”だけじゃない
URロボより安価に収まる「シリンダ方式」という選択
ピックアンドプレース(Pick & Place)は、部品をつかんで所定位置へ置く自動化の基本動作です。
昨今は、協働ロボット(例:URシリーズ)での実装が一般的になりましたが、動作が単純で位置と姿勢が明確な工程では、エアシリンダ/エレシリンダ/ロボシリンダ等の“シリンダ方式” の方が初期費用を抑えやすく、立上げも短期で済むケースが多くあります。
なぜシリンダ方式が安価になりやすいのか
要点
- 機構・制御がシンプル:必要軸数が少なく、I/OもON/OFF主体(エレシリンダなら簡易位置決め)。
- 部品単価が低い:ロボット本体・コントローラ相当の高額機器が不要。
- タクト適合が容易:短ストロークの高速往復が得意。
- 教示が最小限:ストッパ・V溝・テーパーで受動アライメントを効かせれば、教示点は端点中心で完結。
「固定ピッチ・固定姿勢・反復」 がキーワードの工程では、シリンダ方式が費用対効果に優れる傾向があります。
『エアシリンダ・エレシリンダ・ロボシリンダの違い』
自動化設備で直線動作を担うアクチュエータには、いくつか種類があります。
代表的なのが エアシリンダ・エレシリンダ・ロボシリンダ です。
- エアシリンダ
圧縮空気で動作する最もシンプルな方式。
安価で速いですが、精度は低く端点制御のみ。 - エレシリンダ
ステッピングモータを使った電動シリンダ。
エアレスで省エネ、中間位置決めが可能。
「エアシリンダ以上、ロボシリンダ未満」の性能。 - ロボシリンダ
サーボモータ+ボールねじ駆動。
±0.01mmの高精度制御が可能で、多点位置決めや速度制御も柔軟。
高機能だがコストは高め。
構成の考え方
代表例
① エアシリンダ方式
- Z軸
-
エアシリンダ(上下降)
- 把持
-
真空パッド+真空発生器(または簡易メカチャック)
- 位置決め
-
受け治具側のV溝・テーパーガイド・ピンでセルフアライメント
- 制御
-
電磁弁のON/OFF、近接・リードスイッチで端点確認
- 用途
-
薄板・樹脂成形品の短距離ピック&プレース、固定ピッチ搬送
② エレシリンダ方式(電動)
- Z軸
-
エレシリンダ(簡易多点位置決め)
- 把持
-
真空または電動グリッパ
- 位置決め
-
ガイド兼用の斜めアプローチ(チルト挿入)で落とし込み
- 制御
-
I/Oまたはフィールドバスで位置番号呼び出し
- 用途
-
端点だけでなく複数高さが必要、微妙な押付量調整が欲しい場合
③ ロボシリンダ方式(高精度・多機能)
- 制御
-
専用コントローラやフィールドバスで位置・速度・推力を柔軟に設定
- Z軸
-
ロボシリンダ(サーボ+ボールねじで高精度制御)
- 把持
-
真空、電動グリッパ、必要に応じて角度付き把持にも対応
- 位置決め
-
治具ガイドに加えて、多点位置決め・速度/加速度の細かな調整が可能
- 用途
-
製品差や段差があり、やさしく置きたい、高さ/姿勢を細かく変えたい、将来の工程追加を見込む場合に有利
URロボットが有利な条件(バランスの見極め)
- 多品種・高頻度段取り替え
教示点の切替やビジョン連携で柔軟に対応。 - 多軸合成の軌跡が必要
角度付き把持、姿勢遷移、干渉回避が複雑。 - 後工程の拡張余地
将来、検査・組付け・ねじ締めなど工程統合を見込む。 - 位置・姿勢のばらつきが大きい
ビジョン補正や力制御が必須。
『将来』の柔軟性・拡張性を買うならUR
『現状』の単純反復に絞るならシリンダ方式が有利。
『将来』の柔軟性・拡張性を
買うならUR
『現状』の単純反復に
絞るならシリンダ方式が有利。
ご相談ください
三協デザインソリューションでは、まずは「シリンダで最小構成」から「将来URへ拡張」まで、段階的な提案が可能です。
簡単なスケッチや現場写真があれば、概略機構案(シリンダ構成 or UR構成)と概算を比較提示いたします。
下記お問い合わせフォーム、またはお電話からお気軽にご相談ください。